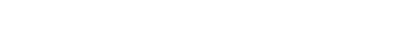「2019年 日本の広告費」で、インターネット広告費は初めて2兆円を超え、テレビを逆転したというニュースが話題になりました。
インターネットの進展でテレビ放送の環境は激変しています。長年、インターネットをライバルと見做し、距離を置いてきたテレビ局ですが、もはやテレビとインターネットの融合は不可避であり、事実、様々な局面でテレビ局のネットへのシフトが起こっています。もちろん、テレビ局でも手を拱いているだけではなく、積極的にネット事業へ参入。文字通り、放送と通信の融合が進んでいます。今回はテレビとネットのそれぞれの特徴や役割に触れながら、その将来像を探ります。

テレビは見ないけどネットは見るという人が増えてきた…。
総務省がまとめた令和元年版の情報通信白書によりますと、2000年から2015年の我が国における平日1日あたりのテレビ視聴時間は、全体では緩やかな減少傾向で推移しています。年代別では、60代では横ばい傾向にありますが、50代以下は減少傾向で、特に10代及び20代の減少が著しくなっています。近年はこれにSNSの普及が加わり、ネットへの接触時間は右肩上がりです。一方、メディアの信頼度という点では20代も含め、テレビが7割、新聞が6割と高いのに対し、インターネットは各世代とも、2割から3割程度に留まっていて、信頼度においては、マスメディアがインターネットと比べて相対的に高いことが実証されています。
ネットへの視聴時間が増えることは、広告を収入源にしているテレビ局にとっては、大きな打撃です。テレビ各局は徐々にネット事業の拡大を図ってきました。はじめはテキストや番組のPRがメインでしたが、技術的に動画が投稿できるようになったり、SNSが普及したりして、今では必要不可欠なコンテンツの一つになっています。在京キー局の場合、局によっては、自社や見逃し配信サイトで地上波との同時再送信に踏み切ったり、外資系の動画配信サービスを系列に収めて、連携を模索したりする動きも出始めています。さらに、本編では流せなかったコンテンツを「スピンオフ」化して、YouTubeなど動画投稿サイトで配信する試みも盛んです。特に地上波がデジタル化し、すべての番組がファイルベース化して以降、サイトへのアップロードは飛躍的に便利になり、ネットシフトへの拍車に大きく貢献しています。なお、余談ですが、各社の「見逃し配信サイト」は、民放の数が少なく、系列局が不在の地方でも、放送当日のうちに内容が確認できるため、視聴者にとっては、大変、好評ですし、ピンチに陥るとみられていた地方局へも参加のチャンスを提供していて、番組販売をとりまく環境にも大きな影響をもたらしています。
ネットニュース全盛の中で、情報発信力が際立つ「レガシーメディア」
20代以下の若者がネットへシフトするにつれ、ニュースをテレビではなく、ネットで知るユーザーも増えてきました。日本の場合、ヤフーニュースをはじめとして、いわゆる「コンテンツ・アグリゲーター」と呼ばれるポータルサイトが圧倒的なシェアを誇っていますが、そのソース、つまり「ネタ元」を見ると、新聞やテレビといった「レガシーメディア」が殆どです。「レガシーメディア」はそもそも陣容面をはじめ、圧倒的な取材力があり、「一次情報」から「サイド記事」や「雑観」、さらには「解説記事」に至るまで、一つの情報を多角的な切り口で伝えるノウハウに長けています。こうした従来からの「戦力」に加え、最近は動画投稿という新たな展開が加わり、サイトの充実が目立ちます。特に新聞社はこれまで静止画中心のWEB構成でしたが、従来の「写真部」にデジタルの機能を持たせ、事件・事故などの所謂、「発生モノ」を中心に一眼レフで撮影した動画を積極的に掲載するようになりました。一方のテレビ局も在京キー局が24時間ニュースチャンネルをアップロードしているのをはじめ、各地方局も自社のローカルニュースで放送した同録をアップロードするなど、もはや、ニュースをWEBにアップしていないメディアを探す方が難しい状況です。加えて、ネット時代になって、劇的に変わったのは、視聴者からの動画投稿が格段に容易になったことです。先述の「発生モノ」で、テレビ局撮影の動画が足りなかった場合、各局の「スクープ投稿サイト」への動画投稿は威力を発揮しますし、最近は視聴者投稿の動画だけを集めた「面白映像」的な番組も、すっかり市民権を獲得しました。僅か数年前まで、一般視聴者の撮った映像は局への持ち込みが必須だったことを考えれば、こと動画投稿においては、局と一般視聴者の垣根は、殆どシームレス化したといえるでしょう。

個人だけでなく企業もネット動画を使うことが増えてきた
インターネットへの動画投稿は、何もテレビ局だけの専売特許ではなく、最近は個人や企業でも、事業拡張に利用するケースが増えてきました。特に最近、企業や事業者が自社発行する「機関誌」や「事業案内」、「カタログ」、「Webサイト」などを「オウンド(=自社所有の)メディア」と括り、ブラッシュアップを盛んに促す例が見られます。
オウンドメディアは、直接的な商品やサービスの販売活動ではなく、Web上の検索ユーザーに高い価値を与えることが期待できますし、汎用性も高く、ニッチなファン層の獲得が期待できます。また、広告会社などや他社メディアを介する必要がないため、コストパフォーマンスの高さもメリットといえるでしょう。
この他にもSNSを使って、顧客の信頼や共感などを獲得する「アーンドメディア」などへの投稿も有効な手法として、活用されています。こうした自社メディアやSNS上で展開するメディアでも、動画で自社の魅力を訴求することは最早、当たり前になってきました。当然、動画撮影の需要は増大の一途をたどり、慢性的な人手不足に陥ることは論を俟ちません。そして、こうした動画撮影にプロの視点や技術を採り入れることは、クオリティアップに欠かせない要素といっていいでしょう。
クロスメディアでの相乗効果を期待するテレビ局
先述のように、若者を中心に「テレビ離れ」「新聞・雑誌離れ」が増えてきている中、各メディアは、「クロスメディア」という手法で相乗効果を高めていく取り組みを始めています。
クロスメディアとは、一つの商品やサービスに対して、あらゆるメディアを使って、宣伝や販促活動を展開し、相乗効果を高めていく戦略です。メディアミックスの場合は、様々なメディアに対し、ほとんど同じコンテンツを掲載しますが、クロスメディアの場合は、個人に対して、メディアの特徴に合わせて、見せ方や表現などを変えることで、より深い訴求効果を狙います。当然、テレビとネット、PCとスマホで違うコンテンツを用意する必要があり、中でも、テレビ各局はドラマ、バラエティ、ニュース、スポーツとあらゆる分野での応用を実現しています。本業の放送事業、地上波のみならずBS・CS放送やネットを軸にしたコンテンツビジネス等、各メディアの「得意分野」を生かし効果的な組み合わせを模索しています。
これまで、テレビの世界ではどちらかというと傍系やサポートの役割を担ってきたネットが、メインコンテンツの一角を占めるようになるのに、そう時間はかからないでしょう。いわずもがな、動画需要の増大は確実で、当然、プロの出番も増え、多くの人材が必要になります。コロナ禍で、就職難の到来が指摘される中、映像業界の人材は「引く手数多」ですし、培ったスキルは、将来的にも枯渇することは無いでしょう。
テキスト:ナインフィールド
ディレクター 有明 雄介